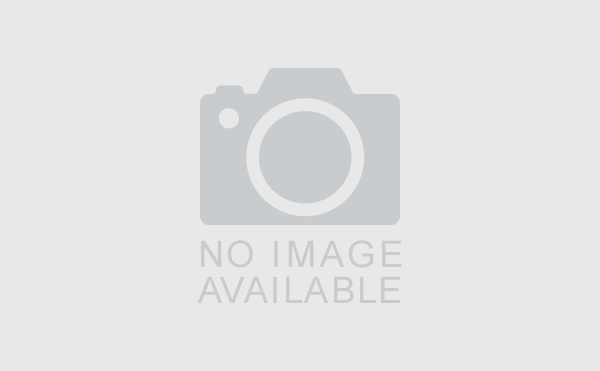稲
日本は古くから瑞穂の国といい、豊かに稲の実る国です。
古来から、稲はわが国の主食であり、稲作は生活の中心でした。そのため、五穀の中でも”嘉穀”と称され新嘗祭や神嘗祭などの国家的行事も行われる稲には、”五穀豊穰”の願いがこめられています。
「稲荷」は稲生りの意で、お稲荷さんは商売繁盛の神様としても信仰されます。稲荷神社の祭神は倉稲魂神(うかのみたま)で、稲荷神社は日本の神社の中でも最も多く約四万社を数えます。五円玉にも使用され、神様にいつも御縁があるという意味も連想させます。
稲紋は、倉稲魂神に奉仕する神官や氏子、関係者などに用いられ、徳川時代には大名・幕臣のあいだにも増えました。また、丸く収め束ねてある図柄は団結の紋という意味も持ちます。
家庭に幸福を招く強運の紋で縁起のよい紋です。