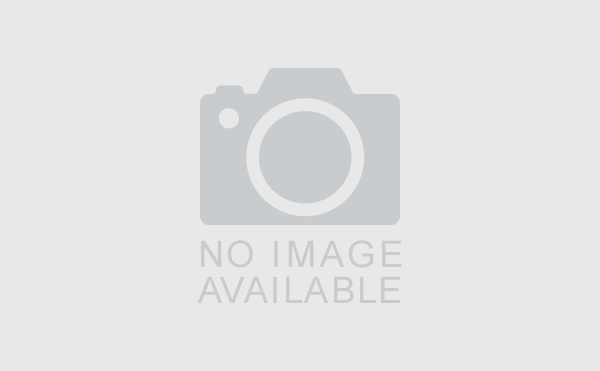沢潟(おもだか)
沢瀉は、池沢などに自生する白い可憐な花が咲く水草です。
多年草で延命長寿を意味します。人の顔(面)に似て葉が高くなる意味で『面高』と呼ばれます。葉の形が矢じりや楯に似ているため、家を守る紋として扱われてきました。また、「攻めても、守ってもよい」ということから、別名勝ち草(将軍草)とも云われ、戦陣の縁起紋として武人に愛好されてきました。古くは、王朝時代に貴族の車に使用され、「沢瀉や弓矢立てたる水の花」と歌に残るように、災いや災難を追い払う紋でもあります。毛利氏の紋として知られていますが、毛利元就が交戦中に進退きわまったその時、沢瀉にトンボの留まるのを見て、「それおもだかに蜻蛉は勝利の印ぞ」と進み勝利を得たといわれます。以後、毛利家の替紋として用いられてきました。
家庭に幸福を招く強運の紋で縁起のよい紋です。