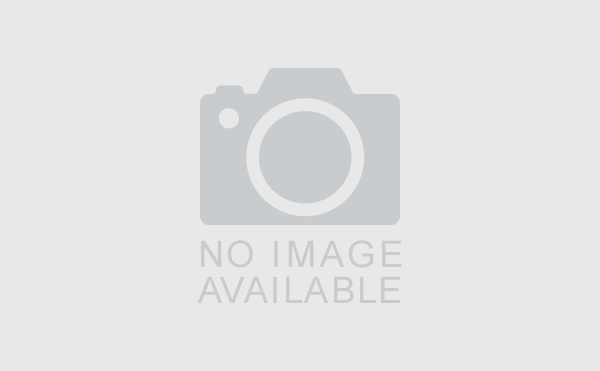筏(いかだ)
筏はもともと文様として用いられたもので、その美しさによって家紋へと転化しました。 形は筏に組んだ材木の数が五・六本、 花は山吹か桜が用いられ、 水をあしらったものもあり風流このうえもありません。
模様としては、江戸前期の佐賀鍋島焼に「花筏文皿」が五彩に美しく描かれ、また京都東山の高台寺にも、秀吉を祀った霊屋の内壇の框に桜の花筏が描かれています。
信濃飯山藩主本多家の定紋は「立葵」でしたが、葵が徳川家の独占紋になってからは花筏紋を用うようになりました。『寛政重修諸家譜』 では、本多家の花筏紋の風流が賞讃されています。そのほか、紀氏流の瀬川氏も使用しています。
家庭に幸福を招く強運の紋で縁起のよい紋です。